written by キリエ
illustrated by マコ
日曜日の住宅街に流しのタクシーは存在しない。
真澄がそう悟ったのは、どうせすぐ拾えると高をくくって、鷹宮邸から辞去した数分後のことだった。
今日は暑くなりそうだ。
五月とは思えない強い日差しが、彼の影をくっきり地面に焼き付ける。
滲み出した汗は、船上の潮風が染みついた皮膚や衣服の不快さを増すとともに、真澄に先ほどの鷹宮邸でのやり取りを思い返させるのだった。
波止場で倒れた紫織は、鷹宮の屋敷へたどり着く寸前に気がついた。
後部座席にいた真澄は紫織に声をかけようとしたが、すぐに思い直した。
クッションに埋まるように半身を預けていた彼女だったが、意識が戻っても身じろぎひとつせず、ただ瞼が開かれたのが変化といえばそうだった。
そして、その瞳はぼんやりととしか言いようがなく、グレーがかった色合いは、まるで死んだ魚の濁った目ようだった。
婚約までした女性に、そんな不気味な印象を持つなんて……。
真澄は目線を前方へ向けると、密やかにため息を吐いた。
車から降り立った紫織は、真澄どころかドアを開けてくれた運転手の助けも借りず歩き出した。
ふらり、ゆらりとやたら上半身が傾ぐ歩みは、まるで大事な部品が欠けた絡繰り人形のような不安定さで、その虚ろな眼と共に彼女の魂はどこかへいってしまったのではないか、と真澄は手を伸ばそうにもたじろぐ。
彼女の心は傷ついている。
魂の片割れを失って。
「お嬢様……!」
甲高い声が響いた。
玄関から女性が飛び出してくる。
滝川という紫織の世話係だった。
目が充血していて、生来の彼女のきつい顔立ちを、より険のある印象に変貌させている。
彼女は紫織に駆け寄ると、本物の母のようにその手を取った。
「まぁ、なんと冷たいことでしょう……! 早くお部屋へお入りくださいませ。お布団を用意してございます。お薬はどうされまして?」
滝川は恐らく運転手に訊ねようとしたのだろう、紫織の後方へ視線を投げかけた。
そして、その時はじめて真澄の存在が目に入ったのか、きゅっとその瞳孔が絞られた。
「速水様……。ご一緒でいらっしゃったのですね?」
尻上がりに上がっていく口調に、抑えようとしても耐えられない怒りがにじみ出ていた。
「いったいこれはどういう……」
「真澄君!」
滝川の声に割り込んできた人間がいた。
この屋敷の主であり紫織の祖父である、鷹宮慶一郎その人だった。
「きみがついていながら、なんてことだ! おお……、紫織。こんなにやつれた顔をして。可哀想に、お前は病弱なんだよ。早く体を休めなさい。滝川、連れて行きなさい」
滝川は全然言い足りないとばかりに真澄を素早くねめつけると、紫織を抱き寄せ、玄関の奥へ消えていった。
威厳のある顔に似合わない猫なで声で孫娘を心配していた鷹宮翁は、仁王立ちで玄関を塞ぐように真澄と向き合った。
そして苦い薬を飲んだように顔をしかめ、真澄を責め始めた。
きみ達はまだ婚約中だ、先日も無断外泊したばかり(恐らく暴漢襲撃の夜のことだと思われる)、紫織は体も弱く、しかも鷹宮家の娘だ、大都芸能が扱う尻軽な女優やタレントとは違う、もちろんきみは紳士的に振る舞っていただろう、だが世間の目はどうか? と。
苦言程度だから拝聴すればいいのだろうが、真澄に反発心のようなものが芽生えたのは、鷹宮翁の女優風情のといったくだりであった。
「僕が一晩過ごした女性は、紫織さんではありません」
従順だと思っていた孫娘の婚約者から、他の女性の影を匂わせる発言が飛び出たことに、鷹宮翁はぽかんと口を半開きにしたまま固まる。
ええい、ままよ、と真澄は、あの鷹通に逆らう震えの裏にある微かな高揚感を頼りに言い切った。
「紫織さんを、これ以上傷つけるのは申し訳なく思っています。大変身勝手ではありますが、できる限り早い内に婚約を解消させていただきたい」
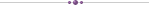
やっと捕まえたタクシーで自宅へ戻った真澄は、シャワーを浴び、軽い食事を取った。
それから仮眠のためにベッドに入る。
すぐに夢を見た。
マヤの夢だった。
正確には、阿古夜に扮しているマヤがいた。

「あの日。初めて谷でおまえを見た時、阿古夜にはすぐわかったのじゃ。おまえが、おばばの言う魂の片割れじゃと……」
初めて出会った時、彼女はまだ中学生だった。
あどけない表情で自分をまっすぐ見つめる大きな瞳が愛らしかった。
あの日から、もう運命はこうなることが定まっていたのだろうか。
「いとしいおまえさま……」
彼女の愛情が、ただ自分だけに注がれている。
ここは夢だが、夢だけの話ではない。
「年も姿も身分もなく、出会えば互いに惹かれあい、もうひとりの自分を求めて止まぬという……」
甲板でのあの夢のような出来事は、きっと一生自分の心を捉えて放さないだろう。
「捨ててくだされ、名前も過去も。阿古夜だけのものになってくだされ」
ああ、きみのためなら速水の姓も、大都のポストも、すべて捨ててもいい……!
やけにリアルな夢だった。
まるで本物のマヤが枕元で演じているようだ。
深い充実した真澄の眠りを破ったのは、携帯の着信音だった。
彼は自分に鞭打つように覚醒すると、その電話に出る。
発信者は意外なことを切り出した。
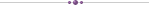
日曜の昼下がり、普段喧騒に包まれるオフィスに当然人影はない。
だが大都芸能の最上階には、既に真澄を待つ人がいた。
水城だった。
挨拶もそこそこに、彼女は手にしていた携帯端末を真澄に見せた。
「朝一に週刊誌の編集部に持ち込まれたそうです。大都芸能と懇意の雑誌社なので、すぐ相談が寄せられました」
水城の平板な口調は、あえて事務的にしているのだろう。
甲板で抱き合うカップルの画像を真澄は作った無表情で眺め、水城に視線を移した。
あ然とした。
水城が泣いていたのだ。
「真澄様……。よおございましたね」
平静を装ったのに、まったくこの秘書には隠し事ができない。
真澄は照れ隠しに咳払いをした。
水城のこんな反応に却って恥ずかしくなってくる。
「この件は、まだ伏せてもらえ。代わりに二つ、三つ宣伝になるようなスキャンダルをつかませてやってくれ」
「まだ、と申しますと……?」
「俺は婚約を解消しようと思う。不利な材料は困る」
「真澄様……!」
水城の涙は途切れた。
感動の余韻に浸っている場合ではないとわかったのだろう。
「よくぞご決断なさいました。ですが、見通しは……」
「ああ、決して明るくないな。だが、俺はやり抜こうと決心している。なにがあっても揺るぐことはない」
真澄は窓に手をついた。
眼下に広がる街並みは、昨日までと今日となにが違うだろうか。
ビルは立替で入れ替わっても、街の印象は変わらぬままで、雨の日も星が見える夜も忙しく立ち働く人々と共にある。
だが俺は、もう孤独ではない……。
「これから忙しくなるな。水城君には迷惑をかけるよ」
振り返った真澄は、朗らかに言った。
ざっとでいいので今後の展望を作ろうと、水城と一緒に作業を始めた。
法的効力のある契約書や覚書の類が入ったA4ファイルは、積み重ねると三十センチを超える。
それを広げて議論を交わすのだが、水城はちょっとした間を突いてナイトクルーズのことを前後の事情も含めて聞きたがった。
あまりあけっぴろげに言うにはマズいところは適当に誤魔化しつつも真澄が素直に白状したら、水城は大げさなぐらい笑い相槌を打ち、さらにつっこんだところを探ってくる。
そうすると段々自分の甲板での言動に、まるで初恋のようなときめきがこみ上げてきて、今さらながら照れる真澄だった。
なにより水城が驚いたのは、紫織どころか鷹宮翁に、すでに婚約破棄を申し入れたことだ。
驚いたというより呆れたか。
前後の見境のない行動に、「恋ですわねえ。重症な」とため息交じりにつぶやかれた。
さらに別荘に誘ったことを話すと、「せっかちすぎる!」と急に切れて、マヤちゃんがかわいそうだかわいそうだと連呼し始めうるさいことこの上なく、真澄は書類に目を戻すとむっつり黙り込んだ。
そして気がつけば、夜になっていた。
日曜日だし、今日のところはこのくらいで、と切り上げようとした真澄に、水城は「そういえば最近……」と、これまた意外なことを言い始めた。
「紫織様のお車で、このようなものを発見したのですわ」
水城はビビットな赤い革の手帳に挟んでいたものを、そっと摘み出した。
真澄はそれを注視した。
写真の切れ端だった。
びりびりに裂かれた欠片にはマヤが映っている。
しかもそのマヤの姿に、真澄は覚えがあった。
「どうして……、こんなものが……?」
「私もおかしく思いまして、それで持ち帰ってしまったのですが……」
真夏の夜の夢でパックを演じているマヤ。
あっ、と真澄は思った。
それはマヤが紫のバラの人へ贈った舞台アルバムの中の一枚に、よく似たものだった。
2011/02/22(火)
スポンサードリンク