written by キリエ
illustrated by マコ
風が運ぶのは、潮の匂い。
そして海鳥の鳴き声も。
マヤはおもむろに瞼を開いていく。
カーテンが揺れる窓の向こうには、澄みきった空がどこまでも広がっていた。
ここは伊豆の別荘。
愛する人に抱かれて目覚めた朝。
ベッドの中には真澄のぬくもりだけが残されていた。
満ちあふれる幸福感に全身が包まれる。
真澄は優しかった。
とっても。
愛するままに身を任せよう……。
そう誓ったのに体の震えを抑えきれない幼い自分を、彼は愛のささやきとキスであたためてくれた。
人は恋をすると、切なさに涙する。
けれど、愛を知ると強くなる。
もう一人ではないと知ったから。
年も姿も身分もなく
出会えばたがいに惹かれあい
もう半分の自分を求めて止まぬという
はやくひとつになりたくて
狂おしいほど相手の魂を乞うると……。
それが恋……。
そういうことか。
阿古夜のセリフの言い回しに気を取られていたが、その心がやっとつかめた気がする。
阿古夜の恋。
なんて情熱的なのだろう。
天女だったはずの彼女が、こんな生の感情を持っていたなんて……!
そういえば梅の谷で、小川を挟んで真澄と向かい合ったとき、自分の魂は確かに真澄の魂とひとつになった。
陰と陽、ふたつに分かれた魂が元の形を成した瞬間、宇宙の果てへ飛んでいき、えも言われぬ素晴らしい体験を味わった。
その奇跡は、昨夜も舞い降りた。
魂のかたわれに抱かれるとは、そういうことだったのだ。
甘いしびれが残る体をベッドから引き剥がし、マヤは身支度を整えた。
愛しい人を追いかけて、階下へ降りていく。
「やぁ、おはよう」
真澄が彼女に照れた笑顔を見せた。
「お……、はようございます……」
「良く眠れたか?」
マヤは小さくうなづいた。
気恥ずかしさに目が合わせられない。
「それは良かった。朝食の用意ができている。せっかくだからテラスで食べよう。マヤもコーヒーでいいかい?」
ソファに座っていた真澄が立ち上がった。
すると、狙い澄ましていたかのように固定電話のベルが鳴る。
「屋敷の者かもしれない。誰にも邪魔されたくないから、携帯の電源は切っているからな」
真澄は肩をすくめてから、受話器を取った。
「なんだ、やっぱり朝倉か。えっ……?」
朗らかな真澄の声が、突如変調した。
マヤは思わず聞き耳を立てる。
真澄は「ああ……」とか「そうか……」とか相槌を打つばかりだったが、その顔色がみるみる青ざめていくのを、マヤは固唾をのんで見守った。
「わかった。すぐ東京に戻る」
そう言って会話を終えた真澄は受話器を戻すと、マヤに向き直る。
彼が切り出すのを、マヤは息を詰めて待った。
あの真澄が動揺を隠さぬまま、震える声でマヤに告げる。
「紫織さんが……、自殺未遂をした」
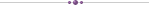
自分は先に東京に戻るが、マヤはここに残っていろ、聖に迎えに来させると言い残し、真澄は慌ただしく出て行った。
残されたマヤは呆然としばらくしていたが、やがてテラスにせっかく用意されていた二人分の食事をどうにかしようと席についた。
とはいえ火入れが絶妙なオムレツも、冷めてしまえばぼそぼそで、普段自分が作る卵焼きと大差がなく、それ以前に食欲が全くなかった。
ぼんやりと海を眺める。
潮風がマヤの髪をなぶっていく。
マヤは食事を諦め、食器類をキッチンに運び入れると、勝手に食材を処分し、洗い物をした。
それが済むとリビングに戻り、手持ち無沙汰のまま時計の秒針がやけに響く中で、ただただ聖の到着を待ちわびた。
ようやく聖の来訪に安堵を覚えたマヤだったが、迎えに来るのが遅くなったと詫びる聖の顔に張り詰めたものを感じ、黙ったまま車の後部座席に乗り込んだ。
一足先に東京に戻った真澄はどうしているのか?
紫織の容態は?
訊ねたいことはあったが、聖にぶつけるのははばかられ、行き場のない不安の渦にマヤは自身を巻き込んだまま、浮かぬ顔で車窓の向こうの伊豆の海を眺める。
昨日、あの人と白い砂浜を散歩した。
ふたりとも童心に返ったように波際ではしゃいで、それから泡を吹くちっちゃなカニを指先でつついて。
海も空もどこまでも澄み切っていて、まるでこの世はふたりきりなようだったのに……。
だが、それはもう遠い記憶のようだ。
不意に景色がぼやける。
涙がひとすじ、マヤの瞳からこぼれていた。
流れる景色が急に止まる。
聖がバックミラーで後部座席をのぞきながら告げた。
「そういえば昼食が、まだでしたよね」
食欲がないと遠慮するマヤの声を無視して、聖が駐車したそこは、全国チェーンのファミレスだった。
賑々しい雰囲気に一瞬、伊豆の閑静なリゾート地との落差をマヤは覚えた。
ひっそり泣いていた自分を、聖が気遣って連れて来てくれたのだから。
マヤは人懐っこい笑みを浮かべ、楽しげにメニューを広げる。
マヤはオムライスを、聖はステーキセットをオーダーし、お冷やを一口すすると、ようやく心の重石が取れた気分になった。
「大丈夫でしょうか、速水さん……。紫織さんも……」
「落ち着いたら連絡するとおっしゃっていましたよ」
マヤはテーブルに置いた携帯電話に視線を落とした。
着信を知らせる点灯は、まだない。
「こんなことになるなんて……」
「後悔しているのですか?」
マヤは首を左右に振る。
「速水さんは婚約しているけど、でもあたし達は魂のかたわれ同志なんです。やっと巡り会えたんです」
「世間だって納得しませんよ」
マヤは、はっと顔を上げた。
「あたしが身を退けば丸く収まるって、聖さんも思ってるんですか?」
「そんなつもりはないんでしょう?」
「はい……!」
マヤは自分が口にした決意の強さを意外に感じる。
そんなマヤを、まるで高貴な宝石を扱うように聖は目を細めた。
「それほどまでに魂のかたわれとは、強い結びつきなのですね。奇跡のようですが」
「奇跡なんかじゃないと思います。誰にだって、きっと存在する。まだ巡り会っていないだけだったり、もうそばにいても気づいていないだけかもしれません。聖さんにも、きっと……!」
「私には戸籍がありませんからね。そんな人間に、人並みの幸せは手に入らないでしょう」
「そんなことありません……! 身分も過去も関係ないんですから」
思わず聖は苦笑いをする。
「魂のかたわれは本当なんです……」
そう言いながらもマヤは、聖は信じてくれていないと感じ取っていた。
聖はそんなマヤを励ますためなのか、「信じましょう……」と口にしたのだった。
食事を取っている最中のことだった。
「マヤ様は本当においしそうに召し上がりますね」
マヤは付け合わせのブロッコリーを頬張ったまま、まじまじと聖を見つめる。
聖は、マヤ様は昔からそうだったが、今日は特に一緒に食事しているだけでこちらも元気になる、一口摂取する毎に体の隅々までエネルギーが行き渡るような心持ちで、なるほど食べることは生きることにそのままつながる、だから食べ物を粗末に扱うと生き方にも現れてくると納得できるし、普段自分は食事に対して生命活動への最低限のノルマだという姿勢だったので、今日気づいたことは新鮮だ、と珍しく多弁に語ったのだった。
食事を終えても、聖はすぐ車に戻ろうとしなかった。
臨海の駐車場の端に見つけたベンチにマヤを促し、これだけは伝えておきたいと語り出す。

それは真澄の過去だった。
彼がどれほど過酷な人生を強いられてきたのか、またそれは生来優しい彼の心をどれだけ傷つけてきたのか、マヤとの出会いからの年月がどんなに彼の心を癒してきたのか、と。
丹念な聖の説明に、自販機で購入したミルクティーの砂糖水のような甘さを啜りながら、マヤは耳を傾け続けた。
「真澄様は強くなろうとなさいました。しかし却ってそれが真澄様を追い詰め、さらに心を傷つける悪循環だったのです。今回の紫織様の手段、真澄様の優しさにつけ込んだ卑劣なものです。また真澄様が心を閉ざされたりしたらと思うと……」
珍しく聖がマヤの前で内実を吐露する。
「真澄様を救えるのは、きっとマヤ様だけです。よろしくお願いいたします」
聖はマヤに向かって頭を下げた。
「よ、よしてください、聖さん!」
マヤは慌てて聖の手を取る。
「あたしがあの人のためにできることって、大してなくって……。でも、なにがあっても、そばにいるって想いだけで……」
「それがなによりも一番です……!」
缶紅茶を飲み終えたマヤはベンチから立ち上がった。
「紫織さん、死にたくなるほどつらかったんですよね。だからって……」
マヤは目の前に広がる海と空に向かって腕を伸ばす。
そして息を大きく吸うと、唐突に紅天女を演じ始めた。
「髪の毛一本、爪一枚、己で造ったものはなにひとつなかろうに。
手も足も、体を流れる赤い血さえ、自分で造った覚えはなかろうが。
我らのこの身はいったい誰が造りたもうたのか?
この身は我らのものであって、我らのものでない。
我らはこの身に宿るもの。
この身を傷つけることが、どれほど大きな罪かわからぬか?
ましてや人の身を傷つけることが、どれほど深い罪かわからぬか?
山や川や森や空は誰が造った?
木や草や鹿やきつねは誰が造った?
鳥や虫や魚は誰が造ったのじゃ?
空に輝くあの太陽は誰が造ったのじゃ?
我らとて同じこと、同じものから生まれしものぞ」
生まれてきた命は奇跡だ。
この海もこの空も、この命とつながっている。
誰もひとりではないのに。
心を閉じた彼女に、そう伝えられたら……!
見入っていた聖が、やっとの思いで声をかけた。
「……紅天女ですね。不思議な世界観だ。とはいえ理解しがたい訳じゃない」
振り返ったマヤは、夢見るような眼差しでささやく。
「ちょっと前に速水さんに言われたんです。俺に紅天女を信じさせてくれ、と。あたし、今ならできそうな気がします。魂のかたわれは本当にあることなんだって、あたしは舞台から伝えたい」
「素晴らしい舞台になりそうですね。マヤ様、存分におやりなさいませ」
聖はにこやかに微笑んだ。
2011/04/04(月)
スポンサードリンク