written by みくう
illustrated by マコ
「ストッーーーーーープ!! おいおい北島、そりゃねえだろうよ!!」
黒沼が大きな声で芝居を止める。役者たちは皆はっとして顔をあげた。視線はすっと主役のマヤへと集まる。
「すいません」
マヤはすまなそうに首を竦め、まわりの役者たちからはため息がこぼれた。
「その中途半端な芝居は一体なんだ?! 上の空で演るなんて、お前紅天女をなめてんのか!! それで姫川に勝てると思ったら……あれ……もしかして……」
黒沼は一瞬遠くを見つめて何かを思案したあと、大きな声で号令をかけた。
「よし、とりあえず休憩! 北島、ちょっとこっちこい」
「は、はい」
バラバラと役者たちがペットボトルとタオルを持って壁際に散っていく中、マヤはおずおずと黒沼のもとに歩いてきた。
「黒沼先生、すいません。あたし、大丈夫ですから。ちゃんと集中して……」
俯き加減に黒沼の前にたったマヤを見る。冴えない表情、集中力を欠いたキレがない演技。考えられる原因はひとつ。黒沼はため息をついた。
「もしかして今日って、若旦那が中国にいっちまう日なんじゃねえか?」
「え……! 先生、ご存知だったんですか?」
目をまんまるにして、驚いているマヤを見て、黒沼は苦笑を浮かべた。
「若旦那から電話をもらったんだよ。だいたいのいきさつも聞いたが、……まあエライこった。あの男がお前のためにすべてを投げ打って、一から出直すっていうんだから」
黒沼がそういうと、マヤは身の置き場がないような表情を浮かべたから、しまったと心の中で舌うちをするがもう遅い。思わず髪の毛をボリボリと掻いた。
「だけどさ、あいつはこうなったことを全く後悔してねえよ。それどころか、本来の自分を取り戻したみたいな、そんな清々しささえあったな。間違いなくあいつは戻ってくるよ。もっと懐の深い人間になってな」
「……」
「だからお前もぼんやりしていないで稽古に身をいれろ…っていいたいところだが、まあ、今日だけは勘弁してやる」
「先生?」
黒沼を見上げているマヤに、苦笑しながら頷いてみせた。
「お前、空港まで若旦那を見送ってこい。しばらくは会えないんだろうから、しっかり顔をみて別れを惜しんでくるんだぞ。そのあとも腑抜けた芝居をしやがったら、承知しねえからな!」
だがマヤの反応があまりよくない。相変わらず冴えない表情をしてため息なんかついている。
「なんだよ。行きたくねえのか?」
「でも速水さんが……稽古が最優先だから、見送りはくるなって…」
あの男なら言いそうなこったと、黒沼は笑いそうになるのを堪えながらマヤのおでこを指でぴん、と遠慮のない力で弾いた。
「い、痛い!!」
額に手をあてて、鳩が豆鉄砲でも食らったようなその顔に、とうとう吹き出してしまった。
「主役のお前が稽古に身がはいらないんだから、どうしようもないだろう? 若旦那には新しい稽古場も提供してもらったし、俺からの餞別だとでもいっとけ」
「先生……」
額をおさえたまま、ぽかんとしているマヤにむかって、黒沼は苦笑した。
「ほら、俺の気がかわらんうちに、はよ行け。今度は船の時みたいに、一緒に乗り込んで、中国まで飛んでいくなよ?」
「い、行くわけないじゃないですか! もう先生ったら……」
マヤの表情が満面の笑みに変わっていく。
「先生、ありがとうございます! あたし、…やっぱり行ってきます!」
「おお、行ってこい。若旦那によろしくな。あ! 稽古は終わりじゃねえからな! 見送ったらさっさと帰ってこいよ?」
黒沼の言葉を最後まで聞かずに、物凄い勢いで駈け出していくマヤの背中を見ながら、黒沼はやれやれと呟いて、緩んだその口元に煙草をくわえた。
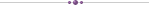
――― いない! いない! いない!
マヤは空港の出発ターミナルを必死で走りまわったけれど、真澄の姿をみつけることができない。頼みの携帯も通じなくて泣きたくなってくる。
――― もしかしたらもう、見送りできない場所までいっちゃったのかな……
携帯は切ってしまったかもしれない。フライトの時間も迫ってきている。どうしていいかわからなくなってきて、幼い子供のように、その場に座り込みたくなった。
そのときだった。マヤの携帯が震える。はっとしてバッグから携帯を取り出すと、探していたその人の名前が、液晶画面に浮かび上がっている。あわてて通話ボタンを押した。
「もしもし!!!!」
『どうしてここにいる?』
いつもの聞きなれた低い声。安心感と一緒に、どっと肩の力が抜けた。
「よかった、携帯が通じて。今、今どこにいるんですか?」
携帯を持ったまま、きょろきょろとまわりを見回すけれど、やっぱりどこにいるかわからない。必死な様子のマヤに、携帯の向こうからため息まじりの苦笑がこぼれた。
『上をみてごらん』
「うえ……?」
視線をあげる。上の階、エスカレーターの傍で、携帯を耳にあてているスーツをきた長身の人。間違いない。真澄だった。ようやく見つけた! マヤの体は勝手に動き出す。エスカレーターをまるで階段のように一気に駆け上って真澄の腕の中に飛び込んだ。真澄が苦笑とともに、マヤの背中に手をまわして抱きとめた。
「よかった……。もう行っちゃったかと思った」
「君からのメール、さっき気づいたんだ。……だが何回も言っただろう? 稽古をサボって見送りになんか来てはいけないって」
心持ち厳しい調子の真澄の声に、マヤは慌てて顔をあげて必死で首を振った。
「違います! あたし、朝一番で稽古場にはいって、一生懸命やっていたんですよ? だけどその…うまく集中できなくて、そうしたら黒沼先生が…さっさと見送りに行ってこいって。速水さんに怒られたら、稽古場を提供してくれたから、俺からの餞別だといえって……」
マヤのいまいち要領を得ない説明でも、真澄には状況が手にとるようにわかったらしい。思わず、というように吹き出した。
「結局それだってサボったのと一緒だろう?」
「サボったんじゃないです! あたしだって、見送りに行きたいのを必死で我慢して、稽古していたのに……そんな言い方はあんまりじゃないですか……」
涙目になって俯き加減になったマヤに、真澄はあわてた様子でこういった。
「悪かった。ついつい君をからかいたくなってしまうのは昔からの悪い癖だな。本当は……日本を離れる前にひとめでいいから会いたかった。だから今、本当は死ぬほど嬉しい」
真澄を見上げる。なんだかまだからかわれているような気がしてしまう。
「ホントに?」
「ホントに」
「嘘じゃなくて?」
「こんな時に嘘なんてついてどうする」
やれやれ、と苦笑して真澄はマヤの頬を愛おしげにそっと撫でた。
「俺だってちゃんとこうやって顔をみて話をしたかったんだ。慌ただしくて、電話でもまともに話せなかったから」
いとおしげに目を細めて見つめる真澄は、年下の恋人を思いやる優しさに満ちていた。彼のその微笑をみていたら、真澄としばらくもう会えないという事実が唐突に迫ってきた。
真澄が婚約を破棄され、大都の社長を辞めてから、マヤはずっとずっと自分を責め続けた。真澄の将来を奪ったのは間違いなく自分なのだ、と。けれど真澄はそんなマヤを何度も抱きしめて、語りかけた。
自分は生き直す。今は生まれ変わったように心が軽い。すべてはマヤのおかげで心から感謝しているのだから、マヤが落ち込むのはおかしいと。その表情は確かに明るく、そして以前にはない穏やかさに満ちていた。それにやはり真澄があのまま紫織と結婚してしまったら、きっと辛くてどうしていいかわからなくなっていただろう。
そうやってマヤも少しずつ現実を受け入れはじめていたけれど、それでもやはり、今日これから真澄が日本からいなくなってしまうと思うと、また自己嫌悪や真澄への申し訳なさがじわじわとこみあげてくる。そしてなによりも真澄が日本からいなくなってしまうと思うと、やはりひどく心許なく寂しい。
それでも笑顔で真澄を送りだそうと決心したのだから。胸をぎゅっと掴まれたような切なさや痛みをこらえ、必死に笑顔を浮かべた。
「よかった、会えて……」
そういって微笑もうとしたけれど、あとの言葉が続かなくなって、思わず真澄の胸に顔をうずめる。真澄はそんなマヤの髪の毛を優しく梳いた。
「電話でもいったが何か困ったことがあったら、聖に言うんだぞ。必ず力になってくれるはずだから」
耳元でささやかれた低い声に、なんども頷く。真澄はいつだって自分のことよりも、マヤのことばかり心配している。誰よりも深くマヤを愛してくれている。そのことがじんじんと伝わってくる。
「それから。これはあえて言わなくていいかと思っていたが、……俺がいない間、親父にも君のことを頼んでおいたから。敵にまわすと恐ろしい人だが、味方につけたら心強い。おそらくあの人なら、君をしっかり守ってくれるはずだから、安心して演技に集中するんだぞ」
「速水さんのお義父さん? 速水会長が……ですか?」
マヤは驚きのあまり声をひそめて真澄をみた。師匠である千草との因縁、さらには真澄のこれ以上ないと思われるような縁談をぶち壊し、真澄を海外へ追いやるきっかけとなったのはマヤだ。速水英介に憎まれているというならともかく、守ってくれるなんて想像もできなかった。真澄はすぐにマヤの心のうちを察して、意味ありげに微笑んだ。
「大丈夫。親父は君のことを、どうにかしようなんて思ってやしないから。むしろ、その逆。君とはもう仲良しなんだと自慢されて、驚いた俺をみたときのあの人の満足そうな顔をみせてやりたいくらいだ。あんみつやらパフェを一緒に食べてメル友になったんだって? 世界広しといえど、あの人にパフェを食べさせることができるのは君くらいなものだろうな」
笑いをこらえてそういう真澄に、ふくれるどころか本気で驚いてしまった。
「ええええっ! パフェのおじさんって速水会長だったんですかっ! お金持ちそうなおじさんだとは思っていたけど、まったくそんなこと思いつきもしなかった!」
今さらながら驚愕顔のマヤに、真澄はどうしても笑いが止まらないとでもいうように言葉を続けた。
「パフェのおじさんってすごいネーミングだな。 なんにも知らなかったとはいえ、あの人とパフェ食べながら楽しく世間話をするなんてありえないぞ」
「だってだって……ぜんぜんそんなこと言ってくれもしなかったし……ああ!!! そういえばあたしったら、梅の谷でおじさんに向かって、速水さんと速水会長の悪口までいっちゃったかもしれない!」
我ながらなんて間抜けなんだろうと、マヤは心底自分が情けなくなった。よくよく考えれば、あんな梅の谷の近くでばったり会うのもおかしいし、千草の所在を教えてくれたこともあった。そんなことを考えあわせれば、あの老人が何者かなんて、すぐわかったはずなのに。真澄が紫のバラの人だったことも長い間全く気がつかなかったことも含めて、自分の迂闊さを嘆かずにはいられなかった。そんなマヤをみて、真澄が苦笑する。
「俺の悪口……ね。想像つくからどんな悪口かあえて聞かないが、おそらく親父もマヤのそういうところが、気にいったんだろうな」
「悪口いったのに、気にいった?」
真澄をぽかんとした表情で見つめていたら、真澄の抱きしめる手に力がこめられた。
「君はどんな冷たい人間の心でも溶かしてしまうような、不思議な魅力があるんだ。それも君の才能のひとつだが……俺にとっては、心配の種だけどね」
どうも真澄の言っていることがぴんとこなくて、目をまんまるにして見上げていると、真澄は苦笑したまま、マヤの額にひとつキスを落としてマヤのぬくもりを確かめるようにしっかりと抱きしめた。
「試演が観れないのは心残りだが、君なら“本物”の紅天女が演れる。俺はそう信じている。確か以前言ったな。紅天女を信じさせてくれ、と。君が本物の紅天女になれたとき、舞台は、舞台ではなくなる。すべては現実になる。観客は時間さえ超えて、奇跡の存在を目の当たりにすることになる。マヤならそれができるから」
マヤをここまで導いてくれた人。けれどその人はもう旅立ってしまう。彼がいなくても自分は奇跡を起こせるだろうか。不安がこみあげてくる。
「速水さん……。できるかな。あたしにそんなことができる? 速水さんがそばにいなくても…」
掠れた声でそういうと、さらに力こめて抱きしめられた。
「できるさ。ずっと君を見てきた俺だからわかる」
真澄の穏やかな低い声。とくとくの音をたてる心臓の音。温かいぬくもり。
真澄は、不器用な自分すべてを受け入れ、心から深く愛してくれている。大丈夫。たとえそばにいなくても心は間違いなくつながっている。思わず真澄の掌をにぎりしめた。
ゆっくりと顔をあげた。真摯な瞳をしている真澄と目があう。この人とはやっぱり生まれ変わるたびに寄り添ってきたのかもしれない、そんな思いが唐突にわきあがってきて、われ知らず言葉が溢れだしてきた。
「だいすき……」
「え?」
声が掠れてうまく音にならなかった。真澄が微かに首をかしげる。もう一度、ゆっくりと、すべての想いをこめて声を出す。
「速水さん、大好き! 何度生まれ変わっても絶対に、あたしは速水さんのことを好きになる」
真澄はマヤの言葉に大きく瞳を見開いた。それから。さざなみのように、柔らかな、優しい笑みが広がっていった。
「俺も。生まれ変わったとしても何度でもみつけだして、きっと永遠に君だけを愛してしまうだろうな」
照れたような笑みとともに、そっと呟かれたその言葉。真澄もマヤと同じ想いを抱いている。魂のかたわれ。真澄への愛おしさがマヤの中で大きなうねりになる。いつのまにかマヤの口元が柔らかな笑みを形作る。

無意識のうちに真澄の首を引き寄せた。
びっくりした表情の真澄の唇に、顔を寄せてそっと唇を重ねた。
何度も何度もついばむようなキスをする。
ふいに真澄がマヤを強く抱きしめた。小鳥のようなキスは、いつのまにか情熱がほとばしるような激しいものへと変わる。
夢中でキスを交わし続ける。
二人のまわりだけ時が止まる。
ただただひたすらに求めあう。
互いをむさぼるような激しさの中に、いたわりや思いやりをも秘めたキス。
長いようで短いようなその時間にも終わりがくる。
名残惜しげに二人の唇が離れた。
みつめったあと。マヤがまっすぐに真澄をみつめながら口を開いた。
「速水さん、あたし、必ず本当の紅天女を演じてみせます。いつか本公演で、必ず速水さんに観てもらえるように、あたし、本当に頑張ります」
「ああ、約束だぞ」
頷く真澄の笑顔をマヤは眩しげにみつめる。
マヤの頭にぽんと手をのせてから、真澄は腕時計に視線を落とした。
「…そろそろ行かなくてはいけないな。船のときのように、また君が一緒に飛行機に乗ってしまったら大変だから、ここでお別れだ」
「パスポートもないのに、そんなこと、できるわけないじゃないですか。黒沼先生と同じイジワルを言うんだから」
真澄がわざとそんな冗談をいったことがわかるから、拗ねたふりをする。このまま潔く笑顔で見送りたい。そう思っていたのに、つい正直な気持ちがぽろりとこぼれる。
「……ギリギリ行けるところまで、見送りしちゃだめですか?」
真澄は苦笑を浮かべて首を振った。
「早く稽古場に戻ったほうがいい。君は主役なんだ。主役がいなくては、芝居は始まらない」
真澄はもう恋人から、長年にわたってマヤを叱咤激励し続けてきた、最大の支援者であり理解者の顔に変わっていた。彼の期待を裏切りたくはない。
「じゃあ、ここで。本当に……体には気をつけてくださいね」
「君こそちゃんと食べるんだぞ。役者は体が資本だからな」
一生あえなくなるわけじゃない。そんなことはよくわかっている。それなのにどうしたことか、いざ別れとなると言葉が出てこない。体も動かない。立ちすくんでしまう。ちゃんと笑顔を浮かべなくてはとも思うのに、泣き顔みたいなヘンな顔になっているような気がする。そんなマヤをみて、真澄はもう一度優しく抱きしめた。
「君が行ったのを見届けてから、俺も行く。ここで君のことを見ているから」
「え……」
耳元でささやかれた言葉。切ない別れの痛みは和らいでいく。かわりに心を満たし始めたのは真澄への愛情。それらは眩い光のように、マヤの身体の奥底にまで差し込んでくる。
マヤは知らず知らずのうちに微笑んでいた。
「あたし、さよならなんて言いません。だって、いつだって速水さんのことを想っているし、また会えるし、いう必要なんてない……から」
「そうだな。俺も言わない」
いままでの辛い経験も、真澄への想いもなにもかも。何かに導かれるようにここまでたどり着いたのはけっして偶然ではない。なぜなら今、あえて集中しなくてもとても自然に、マヤの中の阿古夜がめざめ、鼓動しはじめたのだから。
最後にもう一度だけとマヤは真澄のあたたかい胸の中に顔をうずめ、大きく息を吐く。
そっと顔をあげて真澄と視線を合わせて微笑みを交わし合う。
それから。真澄の腕が解かれたのを合図に、マヤは振り返ってゆっくりと歩き出した。
背中に感じるあたたかい視線に、草木が芽吹くような感覚が体中に満ちていく。目にはみえなくても伝わってくるもの。心を澄ませればはっきりと感じることができる。
それはマヤの内にいる阿古夜にも共振していく。マヤと阿古夜が重なりあって境目がなくなっていく。
――― 阿古夜も、微笑んでる
天女そのままの、たおやかで美しい微笑が、マヤの顔にゆっくりと広がっていった。
-FIN-
2011/05/08(日)
スポンサードリンク